睡眠の質を上げるには?方法や関連成分を紹介

私たちの健康や日々の体調は、睡眠の質によって大きく左右されます。たとえ長時間眠っていても、深い眠りをしていなければ翌朝すっきりと目覚めることはできず、集中力や仕事の効率も低下しがちです。
現代社会では、就寝前のスマートフォンの利用や不規則な生活習慣、ストレス、食事内容などが原因で、眠りの質が低い方が増えています。
今回の記事では、睡眠の質を上げるための生活習慣や環境づくりのポイント、質の低下を招く習慣、さらには改善をサポートする成分などについて解説します。健康の土台である「眠り」を見直し、質の高い休息を手に入れましょう。
睡眠の質とは?
単に眠っている時間の長さだけでなく、眠りがどれほど深くて安定しており、心身の回復につながっているかを示す概念です。入眠がスムーズで、夜中に何度も目が覚めることがなく、朝の目覚めがすっきりとしているのが質の高い睡眠といえます。
反対に、質の低い睡眠では、長時間眠ったつもりでも疲れが取れず、集中力や判断力の低下、日中の眠気など、健康面や生活全般に悪影響を及ぼします。睡眠の質は、レム睡眠とノンレム睡眠のバランスや深さ、中途覚醒の有無、起床時の爽快感などが基準になります。睡眠の質は日常の行動や環境によって大きく変化するため意識的に取り組む必要があります。
睡眠の質を上げる方法

睡眠の質を上げる方法を「生活習慣」と「睡眠環境」の2つの観点から解説します。
生活習慣
規則正しい就寝・起床時間の維持
睡眠の質を高めるには、まず毎日同じ時間に寝起きする習慣を身につけることが重要です。就寝・起床時間が一定になると体内時計が安定し、自然な眠気が訪れやすくなります。休日の寝だめは一時的な回復感はあっても、平日の生活リズムを崩しやすいため注意が必要です。眠気のピークや目覚めのタイミングが安定すれば、深いノンレム睡眠がより長くできます。
適度な運動習慣
日常的に適度な運動を取り入れることで、夜の入眠がスムーズになり深い眠りをしやすくなります。有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど)や軽い筋トレは、睡眠中の成長ホルモン分泌を促進し、身体の回復力を高めます。ただし、就寝直前の激しい運動は交感神経を刺激してしまい、かえって眠りにくくなるため、寝る3時間前までに行うのが理想です。
食事とカフェイン・アルコールの摂取管理
夕食は就寝の3時間前までに済ませ、脂っこい料理や消化に時間のかかる食事は控えると、眠りの質が向上します。また、コーヒーや緑茶に含まれるカフェインは覚醒作用があり、摂取後6時間程度は影響が残るため、午後の遅い時間帯以降は避けましょう。アルコールは一時的に眠気を感じさせますが、眠りが浅くなり中途覚醒しやすいため、深い眠りを妨げる原因となります。
就寝前にリラックスする
質の高い睡眠をするためには、就寝前に副交感神経を優位にするためにリラックスタイムを設けるのが有効です。ぬるめ(38〜40℃)のお風呂に浸かる、アロマを活用する、軽いストレッチ、音楽を聴くなど、自分に合った方法で心身を落ち着かせましょう。ブルーライトを発するスマートフォンやパソコンの使用は脳を覚醒させるため、寝る1時間前からは控えるのが理想です。
睡眠環境
寝室の温度・湿度管理
快適な睡眠のためには、室温と湿度のバランスが重要です。夏は26℃前後、冬は16〜19℃程度が理想とされ、湿度は50〜60%に保つと呼吸が楽になり、喉や肌の乾燥も防げます。温度が高すぎると寝苦しく、低すぎると体が冷えて眠りが浅くなりやすいため、エアコンや加湿器・除湿機を活用して季節や体調に応じた調整を心がけましょう。適切な温湿度は深部体温の自然な低下を助け、スムーズな入眠と深い眠りにつながります。
照明と光環境の管理
光は体内時計に大きな影響を与えるため、就寝前の照明はできるだけ暗く、暖色系に設定するのが効果的です。ブルーライトを発するスマホやPCの使用は極力控え、間接照明や調光機能を活用して徐々に明るさを落とすと、自然な眠気が訪れやすくなります。外光が強く差し込む環境では遮光カーテンやアイマスクを利用するのも有効です。一方で、朝はカーテンを開けて自然光を浴びることで体内リズムがリセットされ、スムーズな入眠と目覚めにつながります。
適切な寝具の使用
寝具は睡眠の質を大きく左右する重要な要素です。マットレスは体圧をしっかり分散し、自然な寝姿勢を保てる硬さや反発力のものを選ぶと快適に眠れます。枕は首のカーブを無理なく支える高さと形状がポイントで、寝返りのしやすさも考慮することが大切です。掛け布団は季節や室温に応じて保温性と通気性のバランスを意識し、快適な温度を維持しましょう。さらに、寝具を定期的に清潔に保つことでアレルゲンやにおいの発生を防ぎ、適切な睡眠環境を維持できます。
音・静けさの確保
外部からの騒音や生活音があると、眠りが浅くなり中途覚醒の原因になります。そのような環境では耳栓などを利用して音を和らげると安定した眠りにつながります。防音カーテンや家具の配置で音を遮る方法も有効です。完全な無音が落ち着かない場合は、川のせせらぎや雨音など一定のリズムの環境音を流すとリラックスしやすく、スムーズな入眠につながることがあります。
睡眠の質が下がる習慣

先述した通り、睡眠の質は日々の何気ない行動や環境が深く関わっています。例えば、就寝や起床の時間が日によって大きく変わる不規則な生活リズムは、体内時計を乱し自然な眠気や深い睡眠の妨げになります。また、寝る直前にスマートフォンやパソコンを使ってブルーライトを浴びたり、刺激的な動画やニュースに触れたりすると、脳が覚醒状態になり入眠が遅れることがあります。
さらに、昼寝を長時間行ったり夕方以降に仮眠を取ったりすると、夜の眠りが浅くなることもあります。日中の運動は睡眠に良い影響を与えますが、就寝直前の激しい運動は交感神経を活発にして体温や心拍数を上げ、入眠の妨げになります。
加えて、ストレスや不安を抱えたまま就寝すると、心身がリラックスできず寝つきが悪くなり、中途覚醒の原因にもなります。このように、生活のリズムや光・刺激の受け方、昼寝や運動のタイミング、精神的な状態などが複合的に作用し、睡眠の質を低下させてしまうのです。
健康食品・サプリの活用もおすすめ
睡眠の質を改善する方法として、生活習慣や環境の見直しに加え、健康食品やサプリメントの活用も近年注目を集めています。体内リズムの調整やリラックス状態の維持をサポートすることを目的に設計された健康食品・サプリも多く、睡眠に悩む人の選択肢のひとつとなっています。特に、忙しい生活やストレスの多い環境で過ごす現代人にとって、日常の食事だけでは補いにくい要素を効率的に取り入れられる点が魅力です。
また、睡眠の質の改善をサポートする健康食品・サプリにも粉末・カプセル・ドリンクなど様々な種類があり、シーンや目的に合わせて選べます。ただし、そうした健康食品やサプリは、あくまで生活習慣改善の補助として活用することが望ましく、規則正しい生活や快適な睡眠環境と併せて取り入れることで、その効果がより実感しやすくなります。
睡眠の質に関連する成分
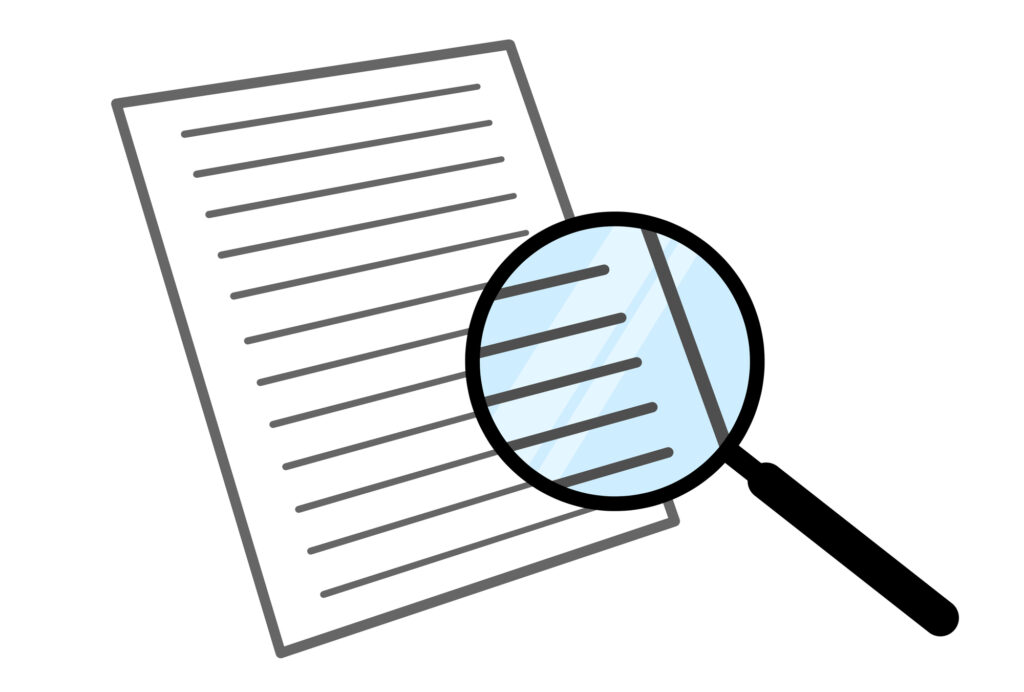
それではここからは、睡眠の質に関連する主な成分を紹介します。
主な成分として以下が挙げられます。
・DHA・EPA
・霊芝
・GABA
・グリシン
・テアニン
・トリプトファン
これらはいずれも睡眠リズムの安定化やリラックス作用、脳や神経の働きに関与する成分であり、それぞれ異なるアプローチから睡眠の質の改善が期待できます。
近年販売されているサプリメントや健康食品では、それらの成分が単独で含まれるのではなく、複数を組み合わせて配合しているケースが多く見られます。例えば、トリプトファンやグリシンなどアミノ酸系の成分を中心に、リラックス作用を持つGABAやテアニンを加えた処方、さらにDHA・EPAや霊芝を補完的に組み合わせた商品もあります。それは、単一成分よりも複数成分の相互作用によって入眠のサポートや深い眠りの維持、ストレスの軽減など、多角的にアプローチできると考えられているためです。
DHA・EPA
DHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)は、青魚などに豊富に含まれるオメガ3系脂肪酸で、脳や神経、血管の健康維持に欠かせない成分です。特にDHAは神経細胞膜の柔軟性や情報伝達機能に関与し、脳の働きをサポートします。EPAは血液をサラサラに保つ作用や炎症を抑える働きがあり、循環機能の改善に寄与します。睡眠との関係では、それらの脂肪酸が神経伝達物質の生成やホルモンバランスに影響し、リラックスや入眠のしやすさに関与すると考えられています。
血流改善効果によって脳への酸素や栄養供給がスムーズになり、睡眠中の脳の回復や記憶整理をサポートする可能性も指摘されています。食事から摂取するには、サバやイワシ、サンマなどの魚を週に数回食べることが推奨されますが、魚をあまり食べない人や必要量を確保したい人はサプリメントで補うのがおすすめです。継続的な摂取が重要で、日常生活や食習慣と合わせて取り入れることで、睡眠の質向上の一助となるでしょう。
霊芝
霊芝(れいし)は、古くから中国や日本で健康維持や滋養強壮に用いられてきたキノコの一種で、「マンネンタケ」とも呼ばれます。硬くて苦味のある特有の風味で、食用というよりは乾燥粉末やエキスとして利用されるのが一般的です。霊芝にはβ‐グルカンやトリテルペン類、多糖類、アミノ酸など多様な成分が含まれ、免疫機能の調整や血流改善、抗酸化作用、ストレス軽減などに関わるとされています。睡眠との関係では、自律神経のバランスを整え、心身をリラックスさせる作用が注目されており、ストレスや緊張によって寝つきが悪い場合や浅い眠りが続く場合のサポート成分として活用されることがあります。
また、血流を促し冷えを和らげる働きも期待され、それが快適な入眠環境づくりに寄与するとも考えられています。霊芝は煎じた茶や健康食品、サプリメントの形で摂取されることが多く、近年は睡眠サポートを目的とした商品にも配合されるケースが増えています。比較的安全とされますが、長期的に取り入れる際は体調の変化に注意しながら、生活習慣の改善と併せて活用することが望ましい成分です。
GABA
GABA(ギャバ、γ‐アミノ酪酸)は、脳内に存在する抑制性の神経伝達物質で、神経の興奮を鎮めて心身をリラックスさせる働きがあります。私たちの体内でも生成されますが、ストレスや不規則な生活が続くとその働きが低下しやすく、落ち着かない状態や入眠のしにくさにつながることがあります。GABAを摂取することで、副交感神経が優位になり、緊張緩和や精神的安定をサポートするとされ、結果的に眠りの深さや夜間の中途覚醒の減少に寄与する可能性があります。
また、血圧降下作用やストレス軽減作用が報告されており、日常的な心身の健康維持にも役立つ成分です。GABAはメロン、トマト、かぼちゃ、キムチ、ぶどう、じゃがいもなどに多く含まれ、近年はチョコレートや飲料などに配合された商品も市販されています。
グリシン
体内で合成可能な非必須アミノ酸の一種で、タンパク質の構成成分として存在しています。甘味があり食品の調味や甘味料としても利用されますが、生理機能面では神経系や代謝に関わる多様な役割を担っています。睡眠との関係では、グリシンが中枢神経に働きかけ、体表面の血流を促進して深部体温を下げる作用が注目されています。
また、グリシンには神経の興奮を抑える抑制性神経伝達物質としての働きもあり、就寝前の心身のリラックス状態のサポートにつながります。食品ではうなぎ、鶏肉、エビ、大豆製品、落花生、ゼラチンに多く含まれますが、近年は粉末やカプセル状のサプリメントとしても市販され、就寝前に摂取することで睡眠の質改善を目的に活用されることが増えています。
テアニン
主に緑茶のうま味成分として知られるアミノ酸の一種で、特に玉露や煎茶に多く含まれています。脳内ではα波の発生を促し、リラックス状態を作り出す作用があることが研究で示されており、精神的な緊張やストレスを和らげる働きが注目されています。睡眠との関係では、就寝前の心身の落ち着きをサポートし、入眠をスムーズにするほか、深い眠りを持続させる効果が期待できます。テアニンは興奮性神経伝達物質であるグルタミン酸と構造が似ており、脳内で神経活動を穏やかにする方向に働きかけると考えられています。
カフェインによる覚醒作用を緩和する働きもあるため、日中のリラックスや夜間の安眠サポートとして活用しやすい成分です。食品としてはお茶から摂取できますが、近年はサプリメントやドリンクなど、濃縮された形の商品も増えています。
トリプトファン
必須アミノ酸の一つで、体内で合成することができないため、食事から摂取する必要があります。肉類、魚、大豆製品、乳製品(チーズ、牛乳、ヨーグルト)、ナッツ類などに豊富に含まれており、人間の健康維持に欠かせない栄養素です。
睡眠の質にも関係があり、体内に取り込まれたトリプトファンは、まず神経伝達物質であるセロトニンの合成に利用されます。セロトニンは「幸福ホルモン」とも呼ばれ、精神を安定させたりリラックスを促したりする作用があります。さらにセロトニンは夜になると睡眠ホルモン「メラトニン」に変換され、自然な眠気を引き起こします。その流れから、トリプトファンは間接的に睡眠の質を高める栄養素とされています。
また、トリプトファンの摂取はストレスや不安の緩和にもつながるとされ、睡眠の浅さや中途覚醒の改善に役立つ可能性があります。取り入れることで、心身のバランスを整え、快適な睡眠をサポートする栄養素といえるでしょう。
睡眠の質を上げるサプリ・健康食品を製造するなら
今回の記事では、睡眠の質を高めるための生活習慣や睡眠環境の改善ポイント、さらに関連する成分について解説しました。規則正しい生活リズムや快適な寝室環境、リラックスできる習慣づくりは、質の高い眠りを実現するための基本です。また、近年では睡眠の質をサポートする健康食品やサプリメントにも注目が集まっており、生活習慣改善の補助として取り入れることで効果を高められる可能性があります。
なお、健康食品やサプリメントの開発をお考えの企業様は、ぜひファーマテック株式会社にご相談ください。当社は健康食品・サプリメントの開発・製造をはじめ、原料調達から品質管理まで一貫してサポート可能です。科学的根拠に基づいた原料選定と高品質な製造体制で、お客様のニーズや市場動向に応じた製品をご提案できます。睡眠サポートをはじめとする機能性食品やOEM開発をご検討の際は、ファーマテック株式会社までお気軽にお問い合わせください。

2016年03月に某私大薬学部を卒業、同年04月より都内の漢方薬局で5年間勤務。チビッ子の育児に専念する為、2021年04月に退職。その後3年間の育児期間を経て、子育てを頑張りながら2024年04月より当社にて管理薬剤師業務に従事。
現在は、チビッ子二人の育児教育を手抜きすることなく、一方で会社員をこなす二刀流の薬剤師ママ。
趣味は、バレーボール。甘いもの好き。






